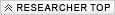Conference
|
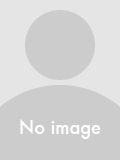
|
Basic information
|
| Name | Taki Akitsugu |
| Belonging department | |
| Occupation name | |
| researchmap researcher code | |
| researchmap agency |
 |
対話篇解釈に基づくと称しつつ、依然その方法の正当性については反省することなく、「プラトンの○○論」という仮構を「精巧に」論ずる論者に対して、「解釈方法論」を説くのではなく、無反省にプラトンについて論ずるかの習慣が、歴史的にいついかなる経緯で発生してきたのかを提示する。上記M.Litt.論文では扱えなかった、古代からFicino訳後の近世までプラトン解釈史を辿り、Schleiermacher以前の「教説的解釈」の伝統を明らかにし、方法論的無反省を招いたSchleiermacherの呪縛を解体する。方法論的に無反省な解釈に対する治癒策として、対話を分析する方法の実践を示す。『パイドン』篇の「哲学者とは死の練習を行うものである」とする従来対話篇内部におけるソクラテスの教説、従ってプラトンの教説と考えられてきたものが、ケベスに内在する「ピタゴラス派的思想」に対する態度が顕在化したものであることを示す。