講演・口頭発表等[R]
|
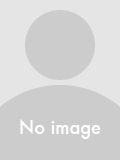
|
基本情報
|
| 氏名 | 姜 東星 |
| 氏名(カナ) | ジャン ドンシィン |
| 氏名(英語) | JIANG DONGXING |
| 所属 | 福祉総合学部 福祉総合学科 |
| 職名 | 助教 |
| researchmap研究者コード | |
| researchmap機関 |
|
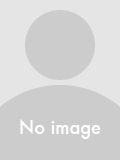
|
基本情報
|
| 氏名 | 姜 東星 |
| 氏名(カナ) | ジャン ドンシィン |
| 氏名(英語) | JIANG DONGXING |
| 所属 | 福祉総合学部 福祉総合学科 |
| 職名 | 助教 |
| researchmap研究者コード | |
| researchmap機関 |