論文[R]
|
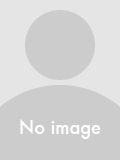
|
基本情報
|
| 氏名 | 瀧 章次 |
| 氏名(カナ) | タキ アキツグ |
| 氏名(英語) | Taki Akitsugu |
| 所属 | 国際人文学部 国際交流学科 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | |
| researchmap機関 |
 |
キケローの弁論術、哲学関係の著作は、キケロー自身の言う所によれば、プラトンのではなく、現存はしないアリストテレスの対話篇形式を模して創作した、文学的作品としての対話篇であって、論文ではない。従来この点に注意を払わずに、「キケローの立場」というものが、対話編主要登場人物の発言と同化されてきた。この誤りを糾しキケローのソクラテス観を分析したのはJohn Gluckerであるが、Gluckerは、この一筋縄では行かないキケローの懐疑主義に光をあてるに留まり、ソクラテスのアイロニーに関するキケローの理解は課題として残したままであった。本論は、この課題に応えるべく、キケローの弁論以外の諸著作を基に、テキストを分析するものである。キケローは、弁論術関係においては、アイロニーの使用そのものを完全には肯定的に評価しない。一方、哲学においては、ソクラテスの「知らないという事以外一切を知らない」という自家撞着的立場をアイロニーと取るか否かを巡り変遷がある。ソクラテスに、またソクラテスに従い、ソクラテスを描くプラトンに、中期アカデーメイア派アルケシラオスと同様の積極的な賢慮による判断遅延の立場を見る一方、最終段階で、キケローは、カルネアデスの「肯定可能性/被説得可能性」という概念を導入して、賢慮による判断の遅延を、「知」を一切否定する事より寧ろ、判断における肯定性を確保することと解釈する事に転換し、ソクラテスやプラトンにその立場を見る事になる。このような「ソクラテスのアイロニー」に関する理解の転換を明らかにし、その原因を考察する。



