論文[R]
|
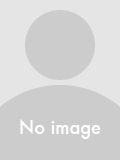
|
基本情報
|
| 氏名 | 額賀 路嘉 |
| 氏名(カナ) | ヌカガ ミチヨシ |
| 氏名(英語) | Michiyoshi Nukaga |
| 所属 | 薬学部 医療薬学科 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | |
| researchmap機関 |
 |
活性中心にセリンをもつクラスAおよびクラスC ―ラクタマーゼは,全体構造および活性中心構造
に類似性があるものの,脱アシル化の機構に大きな違いが存在する。すなわち,クラスA ―ラクタマーゼは活性中心ポケットの底から,上に打ち上げるようにアシル基カルボニル炭素を求核攻撃するのに対 し,クラスCは溶媒側,つまり上方向から活性中心ポケット内に落ちてくるように求核攻撃を行う。ま た,β ―ラクタム系薬が臨床的に利用されるようになって以来,新規 ―ラクタム系薬が開発され,耐性菌が出現することが繰り返されている。その典型的な例が第三世代セファロスポリン系薬を主な標的とし た基質特異性拡張型 β―ラクタマーゼ(ESBL)やカルバペネム系薬を加水分解するカルバペネマーゼの 出現である。本総説では,脱アシル化水に注目して,オキシイミノ系薬とカルバペネム系薬がなぜ,ク ラスA,C β ―ラクタマーゼに対して安定なのか,その一方で,ESBLやカルバペネマーゼはなぜ分解活
性を獲得したのかをX線結晶構造解析の結果より,検討していく。



